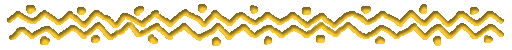
| 通称 : スズキ 学名 : Lateolabrax japonicus 英名 : Sea bass perch |
 |
| スズキ(Common Sea Bass)は, スズキ目スズキ科スズキ属の魚。 現生する魚の中でもっとも大きなグループであるスズキ目の名をもつことでわかるように,日本を代表する食用魚である。体長1mに達する近海魚で,日本の北海道以南の沿岸に分布・生息する魚である。 「出世魚」といわれ,成長するにつれて,呼び名がかわる。満1歳、25cmくらいのものをセイゴ,40cm前後のものをハネ(フッコ),60cm以上のものをスズキと呼んでいる(地方で呼び名が変わる)。 季節移動をする魚で,夏は内湾や河口の汽水域で生活する。だから,この時季は,ルアーフィッシングがおもしろい。冬は内湾をから離れ,やや深いところで越冬する。このとき産卵もおこなわれる。産卵後のスズキは,食欲もあり,イカナゴやイカなどを追って陸に近づいてくる。また,暖かくなるにつれて稚魚も湾内にかえり,汽水域や淡水域にはいりこむ。2月〜3月にかけてセイゴがよく釣れ始めるのはこのためである。 しかし,セイゴのような若魚は淡水域によく入ってくるが,大型になるとほとんど入らなくなる。よって,大物を釣ろうと思えば潮通しのよいところを選ぶのがスズキ釣りの大きなポイントである。 小さいものは,淡水域で捕食・生息するため臭みのあることが多く,味は今ひとつである。とはいえ,塩焼きにすると淡泊で美味である。スズキとなると,白身で美味な高級魚であることは広く知られていることである。夏にはとくに美味となり,値段も冬とくらべてグッと高くなる。刺身,洗い,塩焼き,ムニエル,しゃぶしゃぶなど様々な料理法がありどれも食するものに満足感を与えるものである。釣り魚としても,大変人気の高い魚のひとつである。 中国地方では,島根県の江の川河口でのスズキ釣りが有名であるが,ここでは,稚アユの遡上をねらってスズキが河口まで入ってくる。1メートル級のものが期待できるため県外からの釣り師も多いそうだ。 近縁のヒラスズキは,スズキよりも体高が高く,全長も80cmほどにしかならないと言われているが・・・。外洋に面した沿岸の岩礁帯に多く,川にはいることはない。本州中部から九州にかけてのみ分布し,九州ではヒラスズキをスズキと称する地方が多い。 欧米でスズキにあたる魚は,パーチと言われる。パーチもスズキ目スズキ科に属し,ヨーロッパパーチやアメリカパーチは,スズキ型魚類の原型として言われているそうだ。どちらとも盛んに食用魚として用いられることが多く「スズキ」と日訳されるが,それは,まちがいである。 |
検索等で直接このページにお越しの方へ
トップページはこちらから